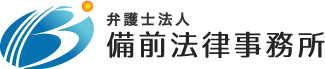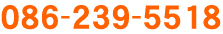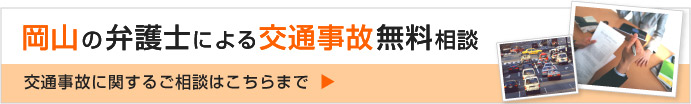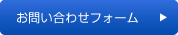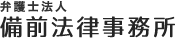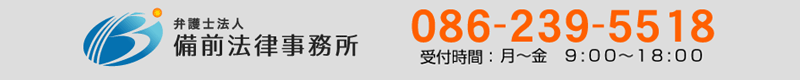弁護士紹介
佐藤 弘一 さとう こういち

略歴
- 昭和46年10月
- 広島県福山市に生まれる
- 平成7年3月
- 東京大学法学部卒業
- 平成15年11月
- 司法試験合格
- 平成16年4月
- 司法研修所入所(第58期司法修習生)
- 平成17年10月
- 弁護士登録(岡山弁護士会)
- 小林裕彦法律事務所に勤務弁護士として就職
- 平成20年10月
- 佐藤弘一法律事務所開設
- 平成25年1月
- 事務所をセンチュリー富田町ビル4階から6階に移転
- 平成25年5月
- 交通事故専門サイト
「岡山 交通事故被害者のための無料相談」を開設 - 平成27年6月
- 弁護士法人備前法律事務所を設立
所属
- 平成23年4月~
平成25年3月 - 岡山弁護士会県民ネットワーク委員会委員長
- 平成24年4月~
平成26年3月 - 岡山商工会議所専門家相談員
- 平成25年4月~
平成28年3月 - 岡山弁護士会民事介入暴力・非弁護士行為等取締委員会委員長
講演実績
- 平成19年4月~
- 不当要求防止責任者講習(岡山県暴力追放運動推進センター)を年1~2回担当
- 平成21年1月
- 労働法に関する講演(企業主催・全4回)
- 平成21年11月
- 「民事介入暴力の傾向と対策」
(岡山弁護士会 秋季県民法律講座) - 平成24年2月
- 「本当は怖い自転車事故」
(岡山弁護士会 冬季県民法律講座)
その他、高校での消費者教育や異業種交流会でのクレーム対策の講演等
メディア
- 平成21年10月~
平成 24年2月 - 「週刊Vision岡山」何でもQ&A
- 平成23年1月~
平成28年12月 - 山陽新聞社「レディア」の「ホームロイヤー」のコーナー連載
ひとこと
私には、弁護士として特に心がけていることが3つあります。
1つ目は、「分かりやすい説明」です。
弁護士の説明が難しいと、相談者や依頼者の方は理解ができず不安になると思います。ですから、私が相談者や依頼者の方に接するときには、とにかく分かりやすく説明をするように心がけています。
2つ目は、「丁寧かつ迅速な仕事」です。
丁寧に仕事をするのは当然のことです。これに加えて、迅速に仕事をするのも重要であると思います。事件が解決するまでの間、依頼者の方の気持ちは休まることがないと思います。できる限り早く事件を解決するために、迅速に仕事をすることを心がけています。
3つ目は、「冷静でありながらも熱く」事件に取り組むということです。
法律家である以上、常に冷静さを忘れてはいけません。しかし、それと同時に「熱さ」を持つことも大事なことだと思います。「依頼者のためになる解決を」という情熱が良い結果を生む最大のエネルギーになりますし、依頼者の方との間の信頼関係の礎になると考えております。
丸野 匡史 まるの ただし

略歴
- 昭和50年9月
- 岡山県倉敷市に生まれる
- 平成15年3月
- 京都大学法学部卒業
- 平成23年10月
- 司法試験予備試験合格
- 平成24年9月
- 司法試験合格
- 平成24年11月
- 司法研修所入所(第66期司法修習生)
- 平成25年12月
- 弁護士登録(岡山弁護士会)
ひとこと
私は、信頼される弁護士であり続けるために特に大事にしていることが2つあります。
それは、プロ意識をもつことと、謙虚さを忘れないことです。
私は、法律のプロとして、相談者や依頼者の方の利益を追求します。 そのためには、相談者や依頼者の方に寄り添うばかりではなく、ときには 相談者や依頼者の方の意向に反することであっても、プロの立場からみた 最善の利益を優先し、丁寧に説明したうえで納得してもらうことも必要で あると考えています。
そして、弁護士は謙虚さを忘れてはなりません。 弁護士が法律のプロであり続けるためには、日々の研鑽が不可欠です。 また、弁護士は法律のプロではありますが、法律以外の分野については、 相談者や依頼者の方の見識に及ばないこともあります。 私は、決して独善に陥ることなく、相談者や依頼者の方の言葉に真摯に耳を 傾けることのできる弁護士でありたいと思っています。
髙田 絵莉子 たかた えりこ

略歴
- 昭和61年9月
- 香川県観音寺市に生まれる
- 平成21年3月
- 早稲田大学法学部卒業
- 平成23年3月
- 明治大学法科大学院修了
- 平成24年9月
- 司法試験合格
- 平成24年11月
- 司法研修所入所(第66期司法修習生)
- 平成26年1月
- 弁護士登録(茨城県弁護士会)
- 茨城県内の法律事務所に入所
- 平成28年2月
- 岡山弁護士会に入会
- 当事務所に入所
ひとこと
私には、弁護士として特に心がけていることが2つあります。
1つ目は、常に研鑽を怠らないことです。 弁護士は、依頼者の方の抱えた問題に対する法的な解決策を考えますが、法律や制度は変遷してゆくものですし、解釈や運用に幅があることもあります。 そこで、依頼者の方により良い解決を導くため、法律や制度の仕組み、その解釈や運用について、専門家として日々勉強し、深く理解しておく必要があります。
2つ目は、依頼者の方の立場に立って考えることです。 これは、依頼者の方が問題を抱えるに至った背景事情やご意向を十分に理解するということで、当たり前のことではありますが、より良い解決策を考える上でとても大切だと思っています。背景事情は人によって様々ですし、同じ問題でも、十人いれば十通りの感じ方やご意向がありうるためです。 そこで、解決策を検討するにあたり、まずはその方の立場に立って考えることを心がけるようにしています。